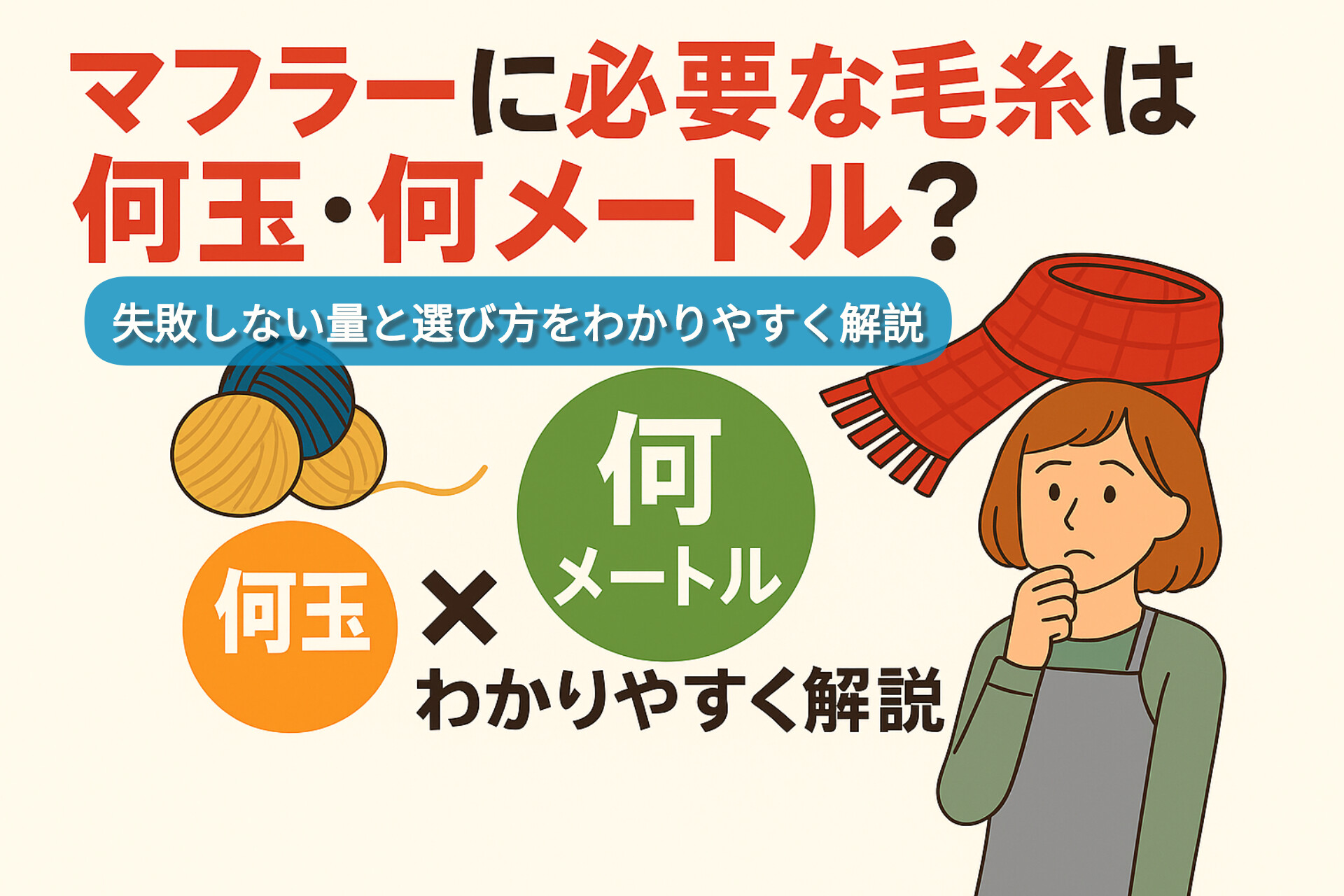マフラーを編むときに一番迷うのが、「毛糸は何玉必要?」「どのくらいの長さがあれば足りるの?」という疑問ですよね。 買いすぎると余るし、足りないと途中で色味が変わってしまう…そんな失敗を防ぐには、太さ・編み方・サイズごとの目安を知っておくことが大切です。
この記事では、マフラーに必要な毛糸の玉数とメートル数の目安をわかりやすく解説します。
さらに、太さ別・サイズ別・編み方別にどれくらい糸が必要なのかを一覧表でまとめ、失敗しない買い方やロット番号の注意点までしっかりカバー。
「あと少し足りなかった…」「同じ色なのに違って見える…」と後悔しないためのコツを、初心者の方にもやさしくお伝えします。
読み終えるころには、あなたのマフラーにぴったりの毛糸量が自信をもって選べるようになります。 これから毛糸を買う方も、家にある糸で足りるか確認したい方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。
マフラーの毛糸は何玉・何メートル必要?<目安と早見表>
「結局、何玉買えば足りるの?」──まずはここが知りたいですよね。
結論から言うと、毛糸の太さ(番手)・1玉の糸長・マフラーの長さと幅・編み方で必要量は大きく変わります。
下の早見表は、一般的な大人用サイズ(長さ約150cm・幅18〜20cm)を想定したおおよその目安。
購入前にラベルの「1玉あたりのメートル表示」を必ずチェックし、迷ったら1玉多めが安心ですよ(同じロット番号で揃えるのも大事)。糸の太さや針の推奨サイズは国際規格があり、Craft Yarn Councilの基準も参考になります。
| 糸の太さ(目安) | 想定糸長(例) | 必要メートルの目安(棒針) | おおよその玉数の目安 |
|---|---|---|---|
| 中細〜合太(Light/DK) | 1玉=約100m〜150m | 約340〜450m | 約3〜5玉 |
| 並太(Worsted/Aran) | 1玉=約90m〜120m | 約340〜450m | 約4〜5玉(迷ったら+1玉で5〜6玉) |
| 極太(Bulky) | 1玉=約60m〜120m | 約225〜340m | 約3〜6玉 |
| 超極太(Super Bulky) | 1玉=約40m〜80m | 約225〜340m | 約4〜8玉 |
ここまでで「必要な総メートル」と「だいたいの玉数」は見えてきましたよね。
マフラー用で失敗しにくいのは、並太で、1玉あたり90〜120mくらいのタイプです。計算もしやすく、途中で足りなくなる事故が起きにくいんです。
「まずは無難にこれでOK」という定番は、下のようなアクリル並太(1玉売り)です。
上記の必要メートルの目安は、欧州ショップ等の実測ベースのガイド(スカーフは太さ別に約225〜760mのレンジ)を参考にしたレンジ化です。
かぎ針は棒針より糸を多く消費するため、おおむね+30%を見込むと安全です。
太さ別の必要量(並太・極太など)
同じサイズを編んでも、糸が太いほど「玉数」は少なく・糸長(m)は短く、糸が細いほど「玉数」は多く・糸長は長く必要になります。
糸の太さは「並太・極太」といった日本の呼び方のほか、DK/Worsted/Bulkyなどの国際区分も併記されることがあります。
針の推奨サイズや概ねのゲージは標準化されているので、Craft Yarn Councilの一覧が目安になります(例:Worsted=4.5〜5.5mm棒針)。
- 並太(Worsted/Aran):大人標準で約340〜450m。模様が多いほど+α。
- 極太(Bulky):大人標準で約225〜340m。ザクザク進むが消費も早い。
- 中細〜合太(Light/DK):大人標準で約340〜450mが目安。細番手は見た目が上品だが時間はかかる。
サイズ別の必要量(大人用・子ども用・ロング・ショート)
必要量は長さ×幅でほぼ決まります。
標準の大人用(約150cm×20cm)に対し、ロングにするなら+15〜30%、ワイドにするなら+10〜25%が目安。
子ども用(120cm×16cm程度)なら、同じ糸で大人の約70〜80%の糸量で足ります。模様編み(ケーブル等)は糸を多く使うので、さらに+10〜20%を見込みましょう。
必要メートルのテーブル化データも各社が公開しており、スカーフ用途での代表値は約225〜450mが中心帯です。
| 対象 | 長さの目安 | 幅の目安 | 必要メートル数の目安 | 使用玉数の目安 (1玉=約40g/約90〜100mの場合) |
|---|---|---|---|---|
| 大人用(標準) | 約150 cm | 約18〜20 cm | 約340〜450 m | 約4〜5玉 |
| ロングサイズ | 約180〜200 cm | 約22〜25 cm | 約400〜550 m | 約5〜6玉 |
| ショート/子ども用 | 約100〜130 cm | 約14〜16 cm | 約240〜330 m | 約3〜4玉 |
| ワイドタイプ/厚手仕上げ | 約150 cm | 約25〜30 cm | 約380〜500 m | 約5〜6玉 |
※上記は並太毛糸(約90〜100m/40g玉)でメリヤス編みした場合の目安です。 毛糸の太さ・素材・編み方によって使用量は変わるため、購入時は毛糸ラベルの「長さ(m)」を必ず確認しましょう。
編み方別の差(棒針・かぎ針・ゴム編み・メリヤスなど)
同じサイズでも編み方で消費は変わります。
一般に、かぎ針は棒針より約3割多めに糸を使います。棒針でも、ゴム編み・かのこ・ケーブルなど凹凸のある模様はメリヤス編みより糸を多く使う傾向。
最適解は小さなスワッチ(試し編み)を作って、10cm×10cmでどのくらい糸を使ったかを測る方法です。その結果をもとに、完成サイズに合わせて必要な総メートル数を見積もれます。
- 棒針・メリヤス:基準。表の値をそのまま採用。
- 棒針・ゴム編み/ケーブル:+10〜20%見込み。
- かぎ針:同サイズなら+30%を目安に加算。
1玉あたりの長さ・重さの見方(グラム→メートル換算のコツ)
購入時は必ずラベルをチェック。多くの毛糸は「1玉=◯g/◯m」と糸長が明記されています。ここが最重要です。
例えば同じ40gでも、糸の軽さや撚りで約88mの糸もあれば120m以上の糸もあります。つまり、「玉数」より「総メートル数」で計算するのが失敗しないコツ。狙いの総メートル数(表の目安)÷ラベルの「1玉のm」で、必要玉数が算出できます。
- 作りたいサイズ(長さ・幅)と編み方を決める。
- 上の早見表から必要メートルを決める(棒針/かぎ針で調整)。
- ラベルの1玉の糸長(m)を確認し、必要m ÷ 1玉m = 必要玉数を計算。
- 同じロット番号で+1玉余裕を持たせる(色ブレ防止)。
針サイズの目安(日本号数⇔mm)を確認したいときは、Craft Yarn Councilの針サイズ表や、日本メーカークロバーの号数・mm対照を参照すると安心です。
長さ・幅で変わる必要量の考え方
マフラーの「どれくらいの長さ・どれくらいの幅」にするかで、必要な毛糸量はかなり変わります。
単に「何玉」だけで考えると、完成して「思ったより短い」「幅が狭くて使いづらい」という失敗も起きやすいんです。
ここでは、標準サイズからロング・ワイド・子ども用まで、長さ・幅による毛糸量の変化を解説しますので、ゆっくり確認して、自分仕様に調整してみてくださいね。
標準サイズ(約150cm前後・幅18〜20cm)の目安
多くの方がまず目安にするのが「長さ約150 cm、幅約18〜20 cm」のマフラー。
これは肩に掛けたときに両端が腰あたりまで来て、ほどよく巻けるバランスの良いサイズです。
実際、幅18〜20 cmというのは、手芸ガイドでも「標準的」な範囲として紹介されています。
このサイズを前提にする場合、先の早見表で出した「太さ別必要メートル数」をそのまま採用してよいです。
ちなみに「標準と同じ長さ・幅なら玉数も変えずに済んだ」という成功者の声も多く、初心者には安心のサイズ感です。幅や長さを変えない分、余計な量を見積もる手間も省けます。
ロング・ワイドにする場合の増やし方
「もっと長く」「もっと幅を広くしたい!」という希望がある方は、毛糸の必要量をプラスして考える必要があります。
たとえば幅を25 cmにしたり長さを180 cmにすると、布量=編み目数×行数が増えるため、使用糸量も必然的に増加します。
ガイドによれば、幅は通常の20 cmより+10〜25%程度、長さは150 cmの目安から+15〜30%が増量目安。
具体的な計算方法としては、「基準メートル数 ×(1+増量率)」で換算すると安心です。
例えば基準が300 mなら長さ+20%=360 mくらいを目安に。玉数で考える場合も同じ比率で増やせば「途中で足りない…」というリスクをかなり減らせます。
ショートや子ども用にする場合の減らし方
逆に「もう少し軽く・短く・子ども用に」と思ったら、毛糸量を少なめに見積もってもOKです。
たとえば子ども用に長さ120cm・幅16cm程度に縮める場合、基準値の約70〜80%で十分という目安があります。
ただし、編み目の密度・模様(ケーブル・フリンジなど)によって使用量が増える点には注意。
「短くても模様編みだから+10%」などの加算も考慮すると安心です。子ども用=そのまま縮めるだけ、という考え方よりも「比率をかける」方式を取り入れると正確性が上がります。
毛糸選びで必要な玉数が変わる理由
「同じマフラーサイズなのに、買う玉数が人によって違うのはなぜ?」──答えは毛糸そのものの特性にあります。
とくに影響が大きいのはゲージ(太さ)、素材、そして撚り(ツイスト)やふくらみ感(ロフト)。ここを理解しておくと、買いすぎ・足りないの失敗がグッと減ります。
公式の標準区分(0〜7のヤーンウェイト)や針サイズの目安はCraft Yarn Councilの資料が参考になります。
ゲージ(太さ)で変わる消費量の違い
ヤーンウェイト(糸の太さ)が太くなるほど1段あたりの面積が増えるので、同じ長さ×幅を編むときの必要メートル数は短く、結果として玉数も少なくなりがちです。
逆に細い糸は必要メートル数が長く、玉数も増えます。太さごとの推奨針サイズやゲージの目安は標準化されているので、まずは自分の糸がどの区分(DK/Worsted/Bulkyなど)かを確認しましょう。これだけで必要量の見積もり精度が一段上がります。
- 細め(Light/DKなど):目が詰まり、同サイズでも糸長は長め=玉数が増えやすい。
- 並太(Worsted/Aran):汎用でバランス良し。標準サイズの基準にしやすい。
- 極太〜超極太(Bulky〜Super Bulky):面積を早く埋める=必要メートルは短め。ただし1玉の糸長が短い製品もあるのでラベル要確認。
また、編み地パターンでも差が出ます。ゴム編みやケーブルなどの凹凸模様は糸消費が増える傾向があり、メリヤス編みよりも“糸を食う”ことがあります。
模様を入れるなら+10〜20%程度の上乗せを見込むと安心です。
素材別の特徴(ウール/アクリル/ブレンド)と仕上がり
同じ太さ表記でも、繊維の種類で仕上がり・必要量の体感が変わります。
たとえばウールは天然のクリンプ(縮れ)によって弾力と保温性が高く、ふっくらと目が立つので少ない段でも厚みを感じやすいのが魅力。
プレゼント用や「チクチクが苦手」な方は、アクリルよりウール混のほうが満足度が上がりやすいです。
アクリルは軽くて扱いやすく、発色や洗濯性に優れますが、同じ番手でも製品によって糸長が大きく違うことがあるため、ラベルの「m/玉」確認が重要です。ブレンド糸は両者の良いとこ取りで、扱いや風合いのバランスが取りやすいのが特徴です。
色味や手触りで選ぶのはもちろん素敵ですが、必要玉数を見積もるときは風合い+糸長の両輪で考えるのがコツ。
たとえば「同じ並太でもA社は1玉120m、B社は1玉90m」なんてことは普通にあります。合計で何メートル必要かを先に決めてから、1玉の糸長で割って玉数を算出するのが、買い間違いを防ぐ最短ルートです。
毛糸の撚り・ふくらみ感による見た目と必要量の差
同じ素材・同じ太さでも、撚り(ツイスト)やロフト(ふくらみ)で仕上がりは変わります。
撚りが強い糸は目がくっきり出て耐久性やステッチ定義が高まる一方、編み地はやや締まって感じることも。撚りが緩い・ロフトが豊かな糸は空気を含みやすく、同じ段数でもふっくら・軽やかに見えます。
見た目の“厚み”が出るぶん、実働の糸長は短めで済むケースもあり、逆にキュッと締まる糸は糸長を多めに見ておくと安心です。
- 多撚り・ハイツイスト:シャープな目=同寸でも糸量がやや増える体感になりやすい。
- ロフト高め(エアリー):軽くて嵩高い=見た目の厚みの割に糸量は控えめで済むことも。
最後にもう一度、ラベルの読み取りを。
必要玉数は「必要総メートル ÷ 1玉あたりのメートル」で決定します。色味のブレを避けるためにロット番号も必ず揃えましょう。これだけで「あと少し足りない…」の買い足しリスクを大幅に減らせます。
失敗しない「買い方」と必要量の決め方
「何玉買えば安心?」に加えて、実は買い方のコツも仕上がりを左右します。
ここでは、ロット番号の揃え方、“+1玉”の考え方、もし足りなくなった時のリカバリー、そして針号数と太さ対応まで、現場感ある方法をまとめました。
読み終えたら、そのままお店やネットで迷わず選べますよ。
同じロット番号で揃えるべき理由
毛糸ラベルにあるLOT(ロット番号)は「同じ染色バッチ」の印。ロットが違うと、同色名でも微妙に色味・トーンが変わることがあります。
スカーフのように面積が広い作品では差が目立ちやすいので、最初に必要量をまとめ買いし、かつすべて同じロットで揃えるのが基本です。もし同ロットが揃わなかった場合は、数段ごとに玉を交互に切り替える“交互使い(alternating skeins)”で馴染ませると段差が目立ちにくくなります。
- ネット購入は到着後すぐにロットを確認。混在していたら未使用のうちに交換依頼を。
- ロット混在で編むときは端で切り替え、または縞・縁取りに活用(意図的な配色に見せる)。
最初は1玉多めが安心(余っても再活用できる)
必要量の見積もりは「総メートル数」で算出し、最後に“+1玉”の余裕を持たせるのがおすすめです。理由はシンプルで、糸長(m/玉)は製品ごとに差があり、しかも途中での買い足しは同ロットが手に入りにくいから。
そもそも糸は半玉単位では買えませんから、少し余るくらいが安全圏です。余り糸はフリンジ・ポンポン・縁編み・ミニ小物に回せば無駄になりません。
- 必要総m ÷ 1玉のm = 必要玉数 → その合計に+1玉(ロット確保の意味でも有効)。
- 余りは季節小物に再利用。色が合えば来季の補修にも使えます。
足りなくなったときの対処法(別ロットの使い方・配色でごまかすコツ)
「あと少し足りない…!」そんなときは次の順で対処しましょう。
- 同ロットの在庫確認:店舗・通販・フリマで番号一致を探す。
- 交互使いで馴染ませる:別ロットしかない場合、2〜4段ごとに旧・新ロットを交互に編む。
- 配色デザイン化:端の数段だけ別ロットにしてボーダーに見せる、フリンジ・縁編みを別ロット(または近似色)で追加するなど、“意図した切り替え”に変換。
色差がはっきり出る場合は、目立ちにくい位置(首元側・端)に配置すると違和感が出にくいです。コミュニティでも、ほどいて数段戻し、交互使いで再開して馴染ませる方法が定番になっています。
かぎ針・棒針の号数と太さ対応の目安
針・フックのサイズは、ヤーンウェイト(0〜7)に応じて推奨mmサイズが決まっています。メーカーや国によって表記が揺れるため、最終判断はmm表記を見るのが確実。
標準はCraft Yarn Councilのチャートが基準で、日本の号数との換算は各社の換算表が便利です。
| ヤーンウェイト | 棒針の目安(mm) | かぎ針の目安(mm) | 日本の代表例(目安) |
|---|---|---|---|
| DK(Light/3) | 3.75〜4.5 | 4.0〜4.5 | 棒針6〜8号前後/かぎ針6/0〜7/0 |
| Worsted(4) | 4.5〜5.5 | 5.0〜6.0 | 棒針8〜10号前後/かぎ針7/0〜8/0 |
| Bulky(5) | 5.5〜8.0 | 6.0〜6.5 | 棒針10〜13号前後/かぎ針8/0〜10/0 |
表はあくまでスタート地点。
最終的にはスワッチ(試し編み)でゲージを取り、狙いのサイズに合うmmへ微調整してください。CYCは「mm表記を基準に」と明記しています。
余った毛糸の活用アイデア
マフラーを編み終えて「余っちゃった…」と思う毛糸、実は宝の山です。
捨てずに活用すれば、環境にも優しく、手作りライフがさらに楽しくなります。
ここでは、余り糸ならではの生きた再活用法を2つの大きなカテゴリに分けてご紹介します。
まずは装飾・アレンジ用途、続いて実用&プチ作品用途です。どちらも家に眠る糸を“ムダなく”使い切るためのアイデア満載ですので、ぜひお楽しみください。
ポンポン・タッセル・フリンジでアレンジ
余った毛糸を使った王道アレンジのひとつが、ポンポンやタッセル、フリンジです。
これらは少量の糸でも華やかになり、マフラーの端・帽子・バッグなどへのワンポイントとして映える人気アイテムです。
実際、「余り糸の使い道」として紹介されるブログでも、これらの装飾アイデアが多数掲載されています。
例えばポンポン:毛糸1〜2玉分程度の長さでも、直径5〜8 cmサイズのポンポン2〜3個を作れることが多く、コストパフォーマンス抜群。タッセルも5〜10 cm程度の長さで数本組合せるだけで“ひらひら感”が出て、作品の印象がぐっとアップします。
- マフラーの端にポンポンを2個付ける → 動きが出てアクセントに。
- 帽子やバッグのファスナーにつけるタッセル → 余り糸の束感がかわいい。
- フリンジを少し長めにして“ウエスタン風”にアレンジ → 無地マフラーのワンランクアップに。
余り糸活用では「量が少ないから使えない…」という思いこみをなくし、むしろ「ちょっとだけカラーを足す」感覚に切り替えるのがコツです。
色や太さが少し違っても“アクセント”なら気になりませんし、むしろ味になります。
ミニバッグ/コースター/ヘアアクセなどのプチ作品
もう一つの活用方法は、余った糸を使って“小ぶりで実用的”な作品を作ること。
例えばコースターやヘアアクセ(シュシュ、ヘアバンド)、さらにはミニバッグやポーチなど。これらは数玉でも十分に完成するため、余り糸を見事に活かせます。
コースター:直径10〜12 cmで仕上げれば、毛糸1玉程度でも数枚作成可能。カラーを組み合わせて“モザイク風”にするのもトレンドです。
ヘアアクセ:シュシュやヘアバンドは1〜2玉あればOK。異なる色や太さの糸を“段ごとに切り替え”すると、オンリーワン感がアップします。
ミニバッグ・ポーチ:巾20〜25 cm程度のサイズなら、並太毛糸3〜4玉で十分に作れます。余り糸が2〜3玉なら“底+持ち手”に足りない分を別糸で補うハイブリッド構成もおすすめ。
- まず余り糸を色・太さ別に仕分け。2〜3色の組合せが美しく見える。
- 次に作品サイズを決定。例えば「コースター10 cm」「小ポーチ20 cm」など。
- 必要玉数が見えたら、足りない分だけ別糸で補う。ただし同系色/同太さが望ましい。
余り糸の活用は、いわば“ハンドメイドのリサイクル”作り手としての満足感も得られます。不要と思っていた糸に“ひと手間”加えて、作品に仕立てると、次の編みものがまた楽しくなります。
よくある質問(FAQ)
ここでは、マフラーを編むときによく寄せられる質問をまとめました。
実際に手芸店や編み物コミュニティでも多く話題になる「玉数」「メートル数」「幅」「模様編み」の4点を中心に、失敗を防ぐためのポイントをQ&A形式でわかりやすくお答えします。
数字だけでなく、実際に編んでいる人の感覚や経験も交えて解説しますので、初めての方も安心して参考にしてくださいね。
並太で大人用マフラーは何玉が目安?
この記事では、大人用標準サイズ(長さ約150cm・幅18〜20cm)を基準にしています。
この条件で並太毛糸(1玉あたり約90〜120m)を使う場合、必要量の目安は約340〜450m。
玉数にすると4〜5玉が基本ラインです。
ただし、模様編み(ゴム編み・ケーブルなど)を入れる場合や、途中で足りなくなるリスクを避けたい場合は、+1玉して5〜6玉で揃えると安心です。
つまり結論としては、
「並太の大人用マフラーは4〜5玉が目安。失敗したくないなら5〜6玉で購入」
という考え方になります。
※毛糸によって1玉の糸長は異なるため、最終的には必要総メートル ÷ 1玉あたりのメートル数で確認してください。
「何メートル」買えば安心?1玉が短い場合の計算方法
「1玉の糸が短いけど、何玉買えばいいの?」という質問も多いですね。基本の考え方はとてもシンプルです。
必要総メートル ÷ 1玉のメートル数 = 必要玉数
たとえば標準的なマフラーで約340〜450mが必要、使いたい毛糸が「1玉=80m」なら、 → 340〜450 ÷ 80 = 5〜6玉。編み方によって+10〜20%増えることもあるので、余裕を見て+1玉あると安心です。
また、糸の太さが極太や超極太の場合は、同じサイズを作っても厚みが出る分、必要メートル数の考え方が変わります。
逆に細い糸は編み目が増えるので、必要メートル数も自然と多くなります。つまり「玉数」より「総メートル数」で把握しておくと、どんな毛糸にも応用できるのがポイントです。
幅は何センチが使いやすい?長さとのバランス
マフラーの使いやすさを決めるのは、実は幅と長さのバランスです。 標準的なバランスは以下の通りです。
| 用途・タイプ | 長さの目安 | 幅の目安 |
|---|---|---|
| 大人用(定番) | 約150cm | 約18〜20cm |
| ロングタイプ | 約180〜200cm | 約22〜25cm |
| ショート・子ども用 | 約100〜130cm | 約14〜16cm |
首元を一重に巻くなら幅18cm前後がちょうどよく、2重巻きやボリューム感を出したいなら22cm前後に広げるとバランスが良くなります。 体格や着こなしに合わせて柔軟に変えてOKです。最近は「スリムタイプ(幅12〜14cm)」の軽めマフラーも人気で、見た目がすっきりして男女問わず使いやすいですよ。
柄編み・模様編みは無地より多く必要?
はい、模様編みは無地より多く毛糸を使います。
理由は、模様を作るために糸を交差させたり、浮かせたりすることで糸の消費量が増えるからです。たとえばケーブル編み・かのこ編み・アラン模様などは、メリヤス編みに比べて10〜25%多めに見ておくのが安全。
特にアラン模様のような立体的なパターンは、太めの糸を使うと見た目も豪華ですが、その分糸が足りなくなりがちです。もし模様を取り入れるなら、1玉多めに確保しておくと安心です。
また、模様が複雑な場合は試し編み(スワッチ)をして、10cm×10cmでどのくらい糸を使うかを測っておくと正確な見積もりができます。これを元に全体の面積で換算すれば、無駄なく必要量を割り出せます。
「かわいい模様にしたら途中で糸が切れた…」という失敗は誰でも通る道ですが、あらかじめ糸量に余裕を持つことで解決できます。作品の完成度も上がり、安心して編み進められますよ。
まとめ:マフラーの毛糸は“余裕を持って選ぶ”のが上手なコツ!
マフラー作りで一番大切なのは、「必要量を正確に見積もり、少し余裕を持って買うこと」です。太さ・長さ・編み方・素材など、すべての条件を考慮して計画的に糸を選ぶことがポイントになります。
まず、標準的な並太毛糸で大人用マフラーを編むなら4〜5玉(約340〜450m前後)が目安です。模様編みや「足りないのが不安」な場合は、+1玉して5〜6玉で揃えると安心です。
ただし、糸の太さや模様の入り方で必要量は変化します。ケーブル編みや模様編みなら+10〜20%、ロングサイズなら+1〜2玉の余裕を見ておきましょう。
そしてもうひとつ大事なのが、同じロット番号で揃えること。ロット違いは仕上がりの色味に微妙な差が出るため、最初に必要量+1玉をまとめて購入するのが鉄則です。
もし余ったとしても、ポンポンやタッセル、ミニバッグなどに再利用できるので無駄にはなりません。
また、編み針やゲージによっても糸の消費量は変わるため、スワッチ(試し編み)で10cm×10cmを確認してから本番に取りかかると安心です。試し編みのデータは、次の作品にも応用できる“自分だけの糸データベース”になります。
最後に、買うときの判断基準をもう一度まとめます。
- 太さ・素材・糸長を確認(「1玉=○m」を見逃さない)
- 必要総メートル÷1玉の長さで玉数を計算
- 同ロット番号+1玉多めで購入
- 模様編みやロングサイズは+10〜20%を加算
この4つを意識するだけで、「足りない」「色が違う」「途中で買い足せない」といったトラブルを防げます。 自分で編んだマフラーは、既製品にはない温かみと満足感があります。少し余裕を持って準備することで、最後まで気持ちよく編み上げられる一枚になりますよ。
次に毛糸を選ぶときは、この記事で紹介した早見表や計算方法を思い出してみてください。「余裕を持って買う=完成までの安心を買う」という気持ちが、編み物上達の第一歩です。